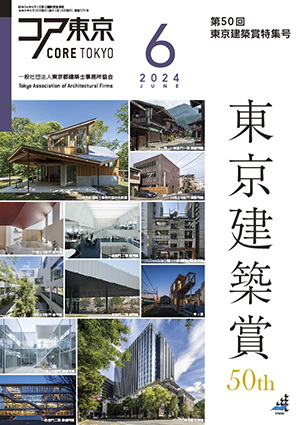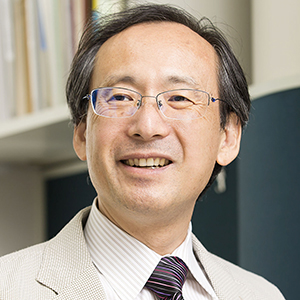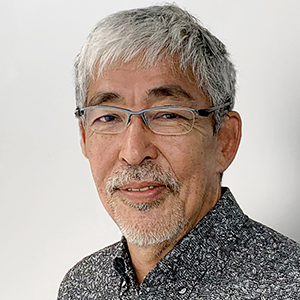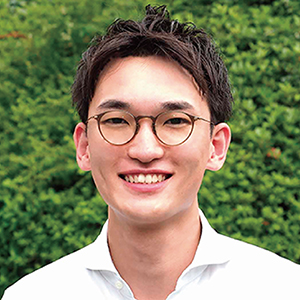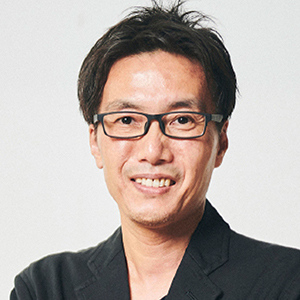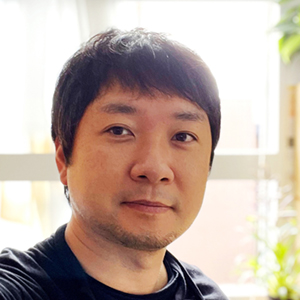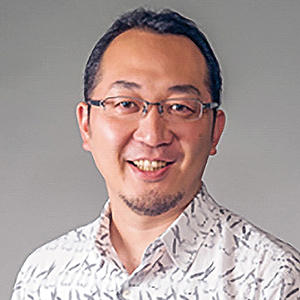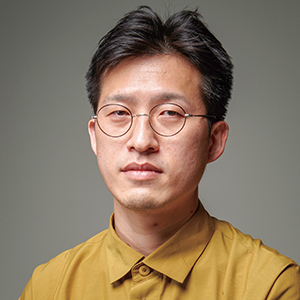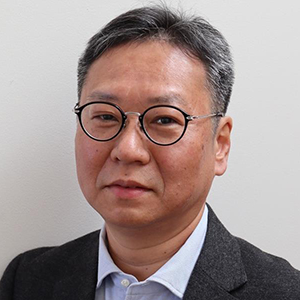令和6年度国への予算要望を提出

自由民主党東京都支部連合会に要望書を提出。
設計等を委託する建築主の利益保護を図る建築士法(以下「法」という)の趣旨を全うするため、建築設計を管理する責任を持つ管理建築士に対し5年に1度の定期的な講習の受講義務を課すよう要望いたします。
併せて、かかる講習を受講した管理建築士の下で業務を行うことにより建築士事務所全体としては十分な業務水準を確保することができることから、建築士の定期講習の受講間隔を3年から5年に延長頂きますよう要望いたします。
法は、建築関係の資格を定めて業務の適正を図り建築物の質を向上させ、もって設計等を委託する建築主の利益を保護することを目的としています(法第1条参照)。併せて、かかる講習を受講した管理建築士の下で業務を行うことにより建築士事務所全体としては十分な業務水準を確保することができることから、建築士の定期講習の受講間隔を3年から5年に延長頂きますよう要望いたします。
この目的を達成するため、建築設計を管理する責任を持つ管理建築士について、法第24条第2項に基づき管理建築士となる資格を取得する際の1回に限り、管理建築講習の受講義務が課されています。管理建築士は、建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括しており、建築士事務所の業務水準を確保するために重要な役割を担っています。
法令改正や技術進歩が行われ業務内容が刻々と変化する中で管理建築士としての業務を的確に実行するためには、管理建築士に求められる知識や技能を常に最新の状態に維持する必要があります。1回限りの講習では、管理建築士に要求される業務水準を維持することは極めて困難です。
つきましては、管理建築士に対して、資格取得時のみならず、5年に1度の定期的な講習の受講義務を課すよう要望いたします。
上記のように管理建築士に5年に1度の定期的な講習の受講義務を課した場合、建築士事務所に所属する各建築士が3年に1度の頻度で定期講習を受講しなくとも、この管理建築士の下で、建築士事務所全体としては十分な業務水準を確保することができます。
つきましては、上記事情を勘案の上、建築士の定期講習の受講間隔を3年から5年に延長頂きますよう要望いたします。
※ 定期的な講習の受講義務の有無及びその年数
宅地建物取引士:5年、不動産鑑定士:受講義務なし、土地家屋調査士:5年
宅地建物取引士:5年、不動産鑑定士:受講義務なし、土地家屋調査士:5年
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ再エネ設計業務を行うにあたっての適正な業務量を算定し業務報酬基準を整備すると共に、業務量に応じた適正な業務期間、設計人・時間を加算して頂きますよう要望いたします。
併せて、省エネ再エネに関する基準の変更に応じて適時に業務報酬基準を改正いただきますよう要望いたします。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネと再エネの促進はどちらも必要不可欠な取り組みです。併せて、省エネ再エネに関する基準の変更に応じて適時に業務報酬基準を改正いただきますよう要望いたします。
建築士は、国、行政の施策に応じ省エネ基準への適合義務制度の対象範囲の拡大等に対応した設計業務を行っています。具体的には、省エネに関しては屋上防水、外壁、サッシ、扉、エレベーター等の設置や改修にあたり設計業務を行うと共に、再エネに関しては太陽光発電設備等を新築建築物や既存建築物に設置等に対し設計業務を行っています。また、木材の利用促進や建築物の長寿命化などの取組も重要であり、ライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅であるLCCM住宅の普及についても取り組んでいます。
特に、新築に比べ構造上・費用上の制約が多い既存建築ストックの省エネ改修や再エネ導入は、頭書の目的を達成するため必要不可欠な要素です。
このように建築士の業務に省エネ再エネ関連業務が付加されているにも関わらず、省エネ再エネ関連業務に関する業務報酬基準が整備されているとは言い難い状況です。その結果、設計業務期間の増大、設計工数の加算が業務報酬に適正に反映されておらず、建築士事務所の経営を圧迫する事態となっています。
つきましては、省エネ再エネ設計業務を行うにあたっての適正な業務量を算定し業務報酬基準を整備すると共に、業務量に応じた適正な業務期間、設計人・時間を加算していただきますよう要望いたします。
国や地方公共団体は省エネ導入、再エネ促進を積極的に促進しており、今後も省エネ再エネに関する基準が変更されることが予想されます。この基準が変更されたにもかかわらず業務報酬基準が改正されない場合、建築士事務所は改正前の業務報酬基準に従って報酬を請求せざるを得なくなり、建築士事務所の経済的負担が増大します。
つきましては、省エネ再エネに関する基準の変更に応じて適時に業務報酬基準を改正頂きますよう要望いたします。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、既存マンションの省エネ改修・再エネ導入を促進するため、長期修繕計画作成ガイドラインに省エネ・再エネの項目を追加頂くと共に、省エネ・再エネ項目を含む長期修繕計画の作成に対する補助制度を充実頂きますよう要望いたします。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネと再エネの促進はどちらも必要不可欠な取り組みです。東京都内のマンションの総戸数は約191万戸※1(令和2年、住宅着工統計)、約4世帯に1世帯が既存マンションに居住しているという東京都の現状を考慮すると、既存マンションの省エネ改修・再エネ導入を促進することは上記目的達成のために極めて重要です。
既存マンションの省エネ改修・再エネ導入を進めるためには、大規模修繕に合わせた設備等の省エネ化や再エネの利用が極めて有効です。大規模修繕は多くの場合長期修繕計画に基づいて実施されるため、長期修繕計画にこれらの要素が盛り込まれていることも極めて重要となります。
しかしながら、令和3(2021)年9月に改正された長期修繕計画作成ガイドラインでは、省エネや再エネに関する項目の記載はありません。各マンションではほとんどの場合長期修繕計画作成ガイドラインに基づいて長期修繕計画を作成することになるため、長期修繕計画作成ガイドラインに省エネや再エネに関する項目がない現状では、既存マンションの省エネ改修・再エネ導入を推進することは極めて困難です。さらに、長期修繕計画に省エネや再エネの項目を盛り込むためには建築士等の専門家の関与が必要不可欠であり、通常よりも多くの費用が必要となります。既存マンションの所有者や管理組合に対する一層の金銭的支援が不可欠です。
つきましては、長期修繕計画作成ガイドラインに省エネ・再エネの項目を追加頂くと共に、省エネ・再エネ項目を含む長期修繕計画の作成に対する補助制度を充実いただきますよう要望いたします。
※1東京マンション管理・再生促進計画(令和4年3月改定、東京都)
カテゴリー:東京都建築士事務所協会関連
タグ:予算要望