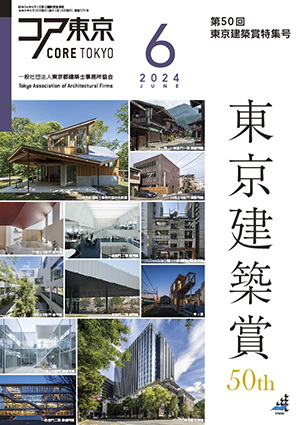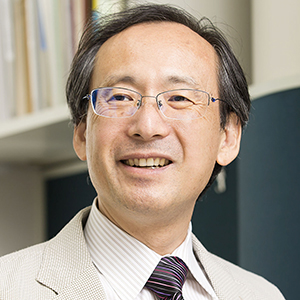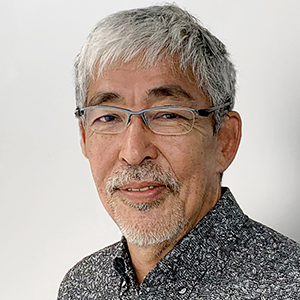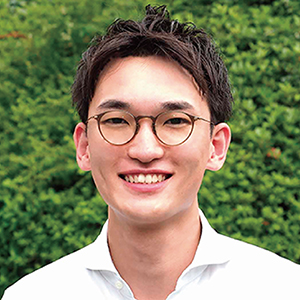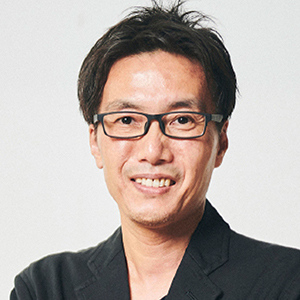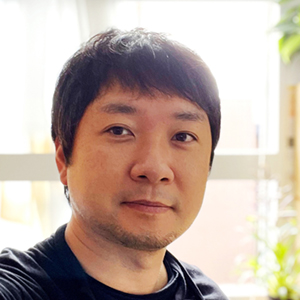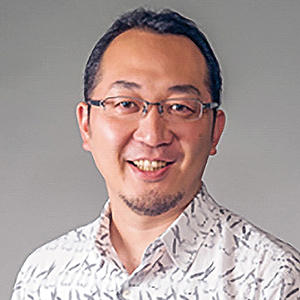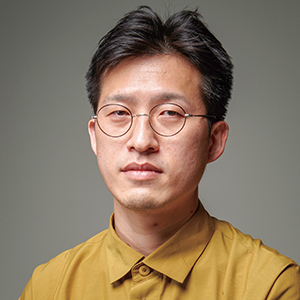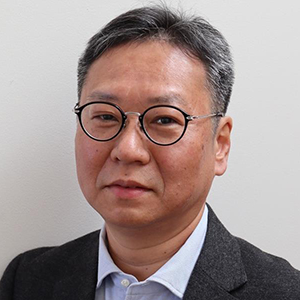松本城の前で記念撮影。

亀田屋酒造 母屋の小屋組み。

石井味噌。

仁科神明宮。本殿(左)、釣屋(中)、中門(右)。

安曇野いわさきちひろ美術館。

碌山美術館。
松本城から酒蔵、味噌蔵
「松本城」の天守には勇壮さを感じた。松本城は戦国時代に建てられ、現存する五重六階の天守のなかで日本最古の国宝の城。場内の庭には全国の主だった城の写真が展示されている。好みもあろうが、城の形は優雅そのものだ。天守に登ると松本市が一望できる。遠くには澄んだ山々が見え、その麓によくこれだけきれいな街をつくったものだと感心させられる。市内はたいへん整備され、店舗は東京の銀座を思わすほどガラス張りの洒落た店が並んでいた。次は明治2(1969)年に創業した「亀田屋酒造店」で酒蔵を見学。建物内には明治時代の道具類がそのままに飾られていた。
この日の最後は「石井味噌」の味噌蔵だった。なんといっても仕込み蔵の樽の大きさには圧倒させられた。
夕方には美ヶ原温泉のホテルに到着、そこで松本市内を一望できる屋上温泉から夜景と温泉を堪能した。
安曇野ちひろ美術館と碌山美術館
2日目は、ホテルからバスで45分ほどの「仁科神明宮」に向かった。ここは神明造の建築物としてはわが国で唯一の国宝である。本殿は江戸時代初期、寛永13(1636)年の建築。この社の廻りにはスギ、ヒノキなどの大木(樹高が50~70mの木もある)に囲われ、不思議な冷気を感じさせる。境内や周辺の森は長野県の天然記念物に指定されている。転じて、明るく広大な公園内にある「安曇野ちひろ美術館」を見学した。絵本画家いわさきちひろと世界の絵本画家の作品を収蔵する世界最大規模の絵本美術館で、平成9(1997)年にオープンした。設計者は内藤廣(内藤廣建築設計事務所)。公園に接続する敷地は面積11,288㎡、延床面積3,206.65㎡。構造はRC造一部鉄骨造で、木造は小屋部のみだが、インテリアは木が多用され、RC構造に現地信州の木材を十分に活用した建物となっていた。また、絵画の展示方法も工夫がされ飽きさせないルートがつくられていた。
最後に「碌山美術館」に向かった。今井兼次の設計で、1958年の開館。日本近代彫刻の扉を開いた荻原守衛(碌山)は、パリで生活していた時代に彫刻家ロダンに会い、その影響を受けて日本で活動した。展示された彫刻はどれも動き出しそうな迫力があった。
ひとつの地域にこれだけ見るべき建造物が点在しているところはあまりないのではないか。自然と一体になり澄んだ環境の中での生活、またはさりげなく文化財を展示しているところが素晴らしいと思えた。有意義な研修会であった。

奥山 安雪(おくやま・やすゆき)
建築家、建築設計アトリエ80主宰、東京都建築士事務所協会北部支部
1953年生まれ/野地建築設計事務所を経て1980年に独立/趣味は「書道」と「躰道」という武道
1953年生まれ/野地建築設計事務所を経て1980年に独立/趣味は「書道」と「躰道」という武道
カテゴリー:支部 / ブロック情報
タグ:TAAFフォーラム