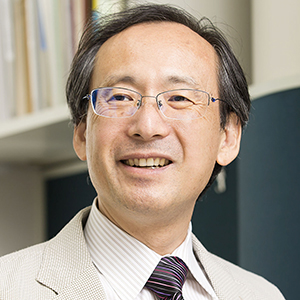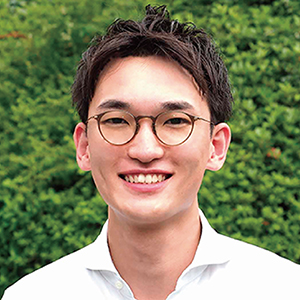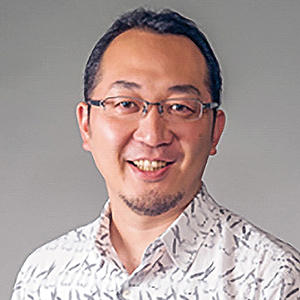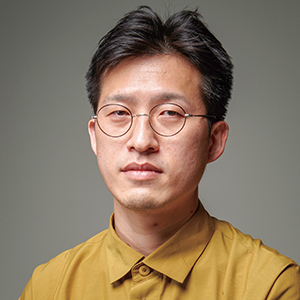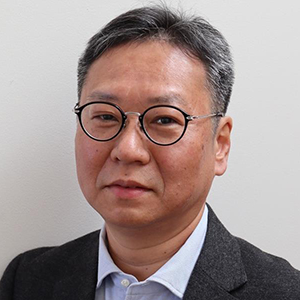研修会「意匠法と建築物の意匠」
法制委員会|令和3(2021)年11月26日@本会会議室
大森 文彦(東京都建築士事務所協会顧問弁護士)
村上 淳(東京都建築士事務所協会理事・法制委員会委員長・中央支部、株式会社山下設計)
村上 淳(東京都建築士事務所協会理事・法制委員会委員長・中央支部、株式会社山下設計)
改正意匠法の施行により、令和2(2020)年4月1日から建築物・内装の意匠登録が可能となった。令和3(2021)年末の時点で登録済の建築関連の意匠はすでに数百件に上っているが、建築設計の現場からは、登録済みの意匠に対してどの程度の類似で権利を侵害していると認定されるのか、そもそも際限なく増え続けるように見える登録意匠の中を検索、類似性を確認することの困難さ等々、制度発足後2年近くを経過しても、まだ戸惑いが収まっていないというのが実感である。
法制委員会では、この改正意匠法について改めて理解を深めるために、当協会の顧問弁護士の大森文彦先生に講師をお願いして、令和3(2021)年11月26日に研修会を開催した。ここでは当日の講義の内容を要約してご紹介する。

この中で特に建築設計と関わりがあるのは、「著作権」と「意匠権」のふたつである。このふたつの権利の対比でいえば、それを保護する目的が、「意匠権」では「産業の発達に寄与すること」、すなわち産業上利用できるかどうか、という背景があるのに対し、「著作権」では精神活動の成果としての優れた文化を保護しようというところに違いがある。これに伴って、その権利がいつ発生するのかという点が両者では大きく異なり、「著作権」は優れた著作物を創った時点で権利が自然に発生するのに対し、「意匠権」は意匠を創作しただけでは権利は発生しない。その意匠が特許庁に登録されて、初めて意匠権という権利が発生する。
しかしながら、今回の改正での最大の変更点となった、保護される対象がそれまでの物品だけから、建築物と内装という不動産に類するものまで拡張されたことが、デザインを活用した経営とどのように関連するのか、あまり納得のいく説明がなく、真相がよくわからないところがある。
ただ、世界に目を向けると、アメリカやヨーロッパにも意匠を保護する法制度があり、その運用に違いはあるものの、いずれにも建築の意匠が保護対象として含まれており、こうした先行する海外の制度との比較も考えてみる必要がある。
また、著作権との対比で理解することも大事である。著作物として権利が保護される建築物は、所謂、建築芸術と呼ばれるような領域に入っているものだけであり、巷にあふれる建物はほとんど著作物として認められないという状況がある。そして、そこまでに至らない「ビジネスに活用できる建築意匠」は、剽窃から十分に保護されているのか、という疑問が残り、今回の改正ではその空白部分を取り込んで、みんな権利として保護しようということにした、と思われる。
①「工業上利用することができる意匠」(第3条第1項)であること。つまり、同一のものを複数作ることができること。
②「新規性」(第3条第1項各号を除くもの)があるもの。すなわち、新規性があると判断されるのは、公然知られた意匠、刊行物やネット空間に掲載されているもの、およびこれに類する意匠、以外のものとされている。「これに類する」を判断するのは、実情は審査官の主観によっていることに注意が必要。
③「創作非容易性」(第3条第2項)があること。つまり、簡単に複製することができないもの。
④「先願者優先」(第9条第1項、第24条第2項)。すなわち、早い者勝ち。
【意匠権の効力】
意匠権の効力(意匠権者が持つ具体的な権利)とは、その意匠を実施する権利、つまり、それを実際に事業に使うことができるという権利である。(第23条)
・ 意匠権をパテント料などと引き換えに他者に与える場合は、「通常実施権」と「専用実施権」のふたつが設定できる。通常実施権は複数者に権利を与えることができるのに対し、専用実施権は特定の者だけに限定して使わせるという違いがある。
【差止請求権と損害賠償請求権】
意匠権が侵害された場合は、侵害された側が「差止請求権」(第37条第1項)と、「損害賠償請求権」(第39条第1項)のふたつの権利を行使できることになる。
・「差止請求権」とは、侵害した側に対して権利実施の差止を要求できる権利で、侵害行為を停止させる効力のほか、侵害される前でも予防的に実施の中止を要求できるという、知的財産権に特徴的な権利のひとつである。
・「損害賠償請求権」は民法では一般的な権利である。しかし意匠権が侵害された場合の、その損害額を立証するのは難しいので、特に意匠法の中には、侵害した側が事業によって得た利益を、全部損害額としてカウントできる、という規定が設けられている。(第39条第1項)
・損害賠償請求権は、侵害した側に故意があった場合のほか、過失によるもの、つまり登録されていたことを知らなかった場合でも、請求権が成立するという点に注意が必要である。
・過失について、意匠法には「過失の推定」(第40条)、すなわち、発生した侵害行為に対して、侵害した側には「過失があったものと推定する」という規定が存在する。つまり、通常は「過失がある」ことを立証するのは、権利を侵害された側だが、この「過失の推定」規定によって、逆に加害者側が自分に落ち度がなかったことを立証しなければならないことになっている。これは非常にハードルが高いので、意匠権を侵害してしまったら加害者側は、ほぼ無過失責任で損害賠償を請求されることを覚悟しておいた方がよいかもしれない。
【意匠法上の「建築物」と「内装」】
・意匠法の中では「建築物」の範囲を具体的に書いている規定はないが、土地の定着物であって人工の構造物はすべて「建築物」とされている。つまり、土木の構造物も意匠法上では「建築物」として扱われる。
・一方、「内装」については第8条の2にその定義が書いてあるが、意匠として登録されるには「内装全体として統一的な美感を起こさせるとき」という条件がついており、この判断にも審査官の主観が入ってくることに注意が必要である。
また一方で、意匠の新規性や、既存の登録意匠との類似性を判断する基準として規定されている「視覚を通じて起こさせる美感」(第2条第1項)については、法律の中ではこれ以上の定義がされていないままであり、つまるところ何を基準に判断しているのかといえば、実際はその審査官が美を感じるかどうかという主観に帰着せざるを得ないと思われる。
このように、登録意匠を他者が模倣するのを制限する制度と、日常の建築設計活動との間に建築設計者が感じるいくつかの違和感に、どう折り合いをつければいいのかといえば、それはこれからの運用にかかっていると考える。
建築物、内装の意匠登録はまだ始まったばかりの制度で、建築設計者と制度の運用者との間で建築文化への認識が共有されている状態ではない。
こうした中で、建築設計者も共感できる「建築の美感を起こさせる」価値観、本当に保護に値するようなデザインとはどういうものかを実務の中で定着させていけるように、制度の運用者と利用者(建築設計者)の双方が、日本の建築文化としての知的な活動に対する価値を、少しでも高めるための会話を続けていくことが重要であろう。
法制委員会では、この改正意匠法について改めて理解を深めるために、当協会の顧問弁護士の大森文彦先生に講師をお願いして、令和3(2021)年11月26日に研修会を開催した。ここでは当日の講義の内容を要約してご紹介する。
(村上 淳/法制委員会委員長 以下、文責:村上)

主な知的財産権(意匠権・特許権・実用新案権・著作権)の比較
知的財産権全般について
知的創作物に対して与えられる権利として、意匠権の他に特許権、実用新案権、著作権があり、その他に商標権(営業上の標識)や育成者権(植物の品種の保護)等がある。この中で特に建築設計と関わりがあるのは、「著作権」と「意匠権」のふたつである。このふたつの権利の対比でいえば、それを保護する目的が、「意匠権」では「産業の発達に寄与すること」、すなわち産業上利用できるかどうか、という背景があるのに対し、「著作権」では精神活動の成果としての優れた文化を保護しようというところに違いがある。これに伴って、その権利がいつ発生するのかという点が両者では大きく異なり、「著作権」は優れた著作物を創った時点で権利が自然に発生するのに対し、「意匠権」は意匠を創作しただけでは権利は発生しない。その意匠が特許庁に登録されて、初めて意匠権という権利が発生する。
改正意匠法について
今回、意匠法が改正された動機としては、世界の有力企業がデザインを中心にビジネス戦略を組み立てている現代において、日本もそれに乗り遅れないように、デザインを活用した経営に対応できる法整備を進めよう、ということが一般的に説明されているようである。しかしながら、今回の改正での最大の変更点となった、保護される対象がそれまでの物品だけから、建築物と内装という不動産に類するものまで拡張されたことが、デザインを活用した経営とどのように関連するのか、あまり納得のいく説明がなく、真相がよくわからないところがある。
ただ、世界に目を向けると、アメリカやヨーロッパにも意匠を保護する法制度があり、その運用に違いはあるものの、いずれにも建築の意匠が保護対象として含まれており、こうした先行する海外の制度との比較も考えてみる必要がある。
また、著作権との対比で理解することも大事である。著作物として権利が保護される建築物は、所謂、建築芸術と呼ばれるような領域に入っているものだけであり、巷にあふれる建物はほとんど著作物として認められないという状況がある。そして、そこまでに至らない「ビジネスに活用できる建築意匠」は、剽窃から十分に保護されているのか、という疑問が残り、今回の改正ではその空白部分を取り込んで、みんな権利として保護しようということにした、と思われる。
意匠登録制度について
【意匠登録の要件──4つのポイント】①「工業上利用することができる意匠」(第3条第1項)であること。つまり、同一のものを複数作ることができること。
②「新規性」(第3条第1項各号を除くもの)があるもの。すなわち、新規性があると判断されるのは、公然知られた意匠、刊行物やネット空間に掲載されているもの、およびこれに類する意匠、以外のものとされている。「これに類する」を判断するのは、実情は審査官の主観によっていることに注意が必要。
③「創作非容易性」(第3条第2項)があること。つまり、簡単に複製することができないもの。
④「先願者優先」(第9条第1項、第24条第2項)。すなわち、早い者勝ち。
【意匠権の効力】
意匠権の効力(意匠権者が持つ具体的な権利)とは、その意匠を実施する権利、つまり、それを実際に事業に使うことができるという権利である。(第23条)
・ 意匠権をパテント料などと引き換えに他者に与える場合は、「通常実施権」と「専用実施権」のふたつが設定できる。通常実施権は複数者に権利を与えることができるのに対し、専用実施権は特定の者だけに限定して使わせるという違いがある。
【差止請求権と損害賠償請求権】
意匠権が侵害された場合は、侵害された側が「差止請求権」(第37条第1項)と、「損害賠償請求権」(第39条第1項)のふたつの権利を行使できることになる。
・「差止請求権」とは、侵害した側に対して権利実施の差止を要求できる権利で、侵害行為を停止させる効力のほか、侵害される前でも予防的に実施の中止を要求できるという、知的財産権に特徴的な権利のひとつである。
・「損害賠償請求権」は民法では一般的な権利である。しかし意匠権が侵害された場合の、その損害額を立証するのは難しいので、特に意匠法の中には、侵害した側が事業によって得た利益を、全部損害額としてカウントできる、という規定が設けられている。(第39条第1項)
・損害賠償請求権は、侵害した側に故意があった場合のほか、過失によるもの、つまり登録されていたことを知らなかった場合でも、請求権が成立するという点に注意が必要である。
・過失について、意匠法には「過失の推定」(第40条)、すなわち、発生した侵害行為に対して、侵害した側には「過失があったものと推定する」という規定が存在する。つまり、通常は「過失がある」ことを立証するのは、権利を侵害された側だが、この「過失の推定」規定によって、逆に加害者側が自分に落ち度がなかったことを立証しなければならないことになっている。これは非常にハードルが高いので、意匠権を侵害してしまったら加害者側は、ほぼ無過失責任で損害賠償を請求されることを覚悟しておいた方がよいかもしれない。
【意匠法上の「建築物」と「内装」】
・意匠法の中では「建築物」の範囲を具体的に書いている規定はないが、土地の定着物であって人工の構造物はすべて「建築物」とされている。つまり、土木の構造物も意匠法上では「建築物」として扱われる。
・一方、「内装」については第8条の2にその定義が書いてあるが、意匠として登録されるには「内装全体として統一的な美感を起こさせるとき」という条件がついており、この判断にも審査官の主観が入ってくることに注意が必要である。
まとめ
「建築の歴史は模倣の歴史」ともいわれる。つまり建築というものは、それまでに実現された建築の意匠、技術をベースにしながら少しずつ時代と共に改良を重ねて変わってくるものである。しかしながら、こうした建築文化の特性について、特許庁の審査官が十分な造詣を持っているかどうかは必ずしも定かではない。また一方で、意匠の新規性や、既存の登録意匠との類似性を判断する基準として規定されている「視覚を通じて起こさせる美感」(第2条第1項)については、法律の中ではこれ以上の定義がされていないままであり、つまるところ何を基準に判断しているのかといえば、実際はその審査官が美を感じるかどうかという主観に帰着せざるを得ないと思われる。
このように、登録意匠を他者が模倣するのを制限する制度と、日常の建築設計活動との間に建築設計者が感じるいくつかの違和感に、どう折り合いをつければいいのかといえば、それはこれからの運用にかかっていると考える。
建築物、内装の意匠登録はまだ始まったばかりの制度で、建築設計者と制度の運用者との間で建築文化への認識が共有されている状態ではない。
こうした中で、建築設計者も共感できる「建築の美感を起こさせる」価値観、本当に保護に値するようなデザインとはどういうものかを実務の中で定着させていけるように、制度の運用者と利用者(建築設計者)の双方が、日本の建築文化としての知的な活動に対する価値を、少しでも高めるための会話を続けていくことが重要であろう。

大森 文彦(おおもり・ふみひこ)
弁護士、一級建築士、東洋大学法学部教授、第一東京弁護士会所属
1951年生まれ/東京大学工学部建築学科卒業/社会資本整備審議会委員(官公庁施設部会会長)/中央建設工事紛争審査会特別委員/司法支援建築会議運営委員会ほか/一級建築士
1951年生まれ/東京大学工学部建築学科卒業/社会資本整備審議会委員(官公庁施設部会会長)/中央建設工事紛争審査会特別委員/司法支援建築会議運営委員会ほか/一級建築士

村上 淳(むらかみ・あつし)
東京都建築士事務所協会理事・法制委員会委員長・中央支部、株式会社山下設計
1956年秋田県生まれ/1982年 株式会社山下設計入社/現在、同社品質管理センター副センター長
1956年秋田県生まれ/1982年 株式会社山下設計入社/現在、同社品質管理センター副センター長